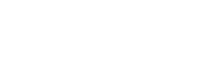窪田望がHANEDA INNOVATION CITYにて発表した現代アート作品『バイナリ化する幽玄』 に関するインタビュー映像が公開されました
キーワード:プレスリリース
2024年11月1日~3日に開催されたHANEDA INNOVATION CITY グランドオープン1周年記念イベント「 あわい – awai 2024 – 」にて展示された、
窪田望が手がけた現代アート作品『バイナリ化する幽玄』についてのインタビュー映像が公開されました。
窪田は、国内外に21のAI特許を持ち、様々なAIの社会実装事業を展開する起業家という顔も持った現代美術家です。
AIの専門家だからこそ見えてきたAIが発展する社会の「無自覚な暴力性」や「排斥されるマイノリティー」をテーマに、作品を創作し続けています。
今回、窪田が作品を通じて提示する問いとは―。インタビュー映像をぜひご覧ください。
作品紹介:
1931年8月25日の羽田空港開港時に6000匹の鈴虫と松虫が最初の乗客として迎えられた。本作品は、鈴虫や松虫の音色を楽しむ平安時代から続く貴族の遊びであった「むしきゝ」の風習を、現代的な解釈で再構築する。来場者のスマートフォンのライトが、特殊なフィルムを通して壁に投影されることで、複雑で美しい色彩の「現代灯火」を生み出す。
会場内には、吊るされた障子が落下する瞬間を再現するインスタレーションが配置され、その周囲には手で破いた和紙が大量に飾られている。脆い和紙は朽ちゆく前の儚い一瞬を感じさせ、何かが崩れ落ちる直前の不安定な美しさを強調している。
作品の核心は、来場者の様子をオンライン会議システム経由で間接的に体験した時にある。観客は美しい現代灯火を目にする一方で、AIによって鈴虫の鳴き声が「ノイズ」として処理され、消し去られてしまっていることに気づくかもしれない。
AIは「ノイズ」と「意味のある音」を区別するが、秋の風流の象徴をAIが掻き消すときに、そこにはある種の排斥が内在化していないだろうか。
これは2024年のAIで起きている問題で、未来ではこの問題は解決されているかもしれない。だが、その時はまた別の「小さき存在」が未来技術によって排斥されている可能性もある。作者は鈴虫の音が聞こえなくなったオンライン会議システムに寄せて思ひを陳べることで、進化するAI社会の中で取りこぼされている存在に目を向けることの重要性を訴えている。
そして、2024年は分岐点である、とも言える。AIが悪意なく、マイノリティを外れ値として排除してしまうとしたら。教師データの元となる私たち自身の中にも、その奥底に潜む排斥がないだろうか。そのことを本作品は静かに問いかける。私たちはどのようにAIと接し、どのような道を見つけるのか。それはAIと無関係だと思い込んでいる私たちにも問いかけられ、その答えは社会の中で乱反射する。
素材 オンライン会議システム、障子、鈴虫寺の立体音響、PVC、大量の和紙
設営協力 シャキメン