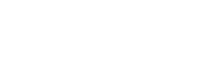窪田望が東京都とアーツカウンシル東京が主催するアーティスト支援プログラムTokyo Artist Accelerator Program(TAAP)の第2期支援アーティストに選出されました
キーワード:プレスリリース

株式会社クリエイターズネクスト 代表取締役社長の窪田望が、東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団
アーツカウンシル東京が主催するTokyo Artist Accelerator Program(TAAP:タープ)の第2期支援アーティストに選出されました。
現代芸術家として「AIが発展する社会の無自覚な暴力性」を問う様々な作品制作に取り組んできた窪田ですが、
2025年は『認知症』をテーマに社会の認識を問う作品づくりの企画・構想を進めています。
窪田は今後、選考委員及びメンターの方々と8か月にわたる継続的な対話をさせていただきながら、
作品の創作活動に邁進して参ります。
2025年11月には作品のコンセプトや制作背景をプレゼンテーションするイベント
「TAAP Live」も開催が予定され、窪田も当イベントに登壇予定です。
支援アーティスト決定の詳細:https://taap.art/news/20250321-0321/
■Tokyo Artist Accelerator Program(TAAP:タープ)とは
TAAPは、アート市場での活躍を希望する美術・映像分野の若手アーティストを支援するプログラムです。
アーティスト自身によって作品を語るプレゼンテーションに焦点をあて、作品を語る力の向上とコンセプト強化の両面からサポートします。
選考を経た支援アーティストへ、自由度の高い制作支援金を支給するとともに、現代アートの多様なスペシャリストと
8ヶ月にわたる継続的なメンタリングを実施し、国内外の現代アート関係者へ向けてスピーチする機会を創出することで、
東京を起点とする若手アーティストの国際的な飛躍を支援します。(TAAP公式サイトより抜粋)
■TAAPでのスケジュール(予定)
メンタリング・プログラム :2025年4月 ~ 2025年11月(8か月間)
成果発表(TAAP Live 2025): 2025年11月
現代芸術家 窪田 望の活動について
コンセプト『外れ値の咆哮』
AIの社会実装事業を推進する企業の経営者としての顔も持ち、国内外に20のAI特許を持つ窪田は、
これまでデータ解析やAI 技術を20 年来研究してきました。
AI開発の現場では入力するデータに異質なデータが混じると良い出力精度が出なくなることがあり、
これを外れ値と呼び、通常はこれを排除します。
窪田は「社会的マイノリティーなどの生活は無視されて良いはずはないのに、進化の過程で見落とされている」と
これらの実態に疑問を感じました。
作品制作を通じて、社会の中で不要とされてきた外れ値の価値を再評価し、
本質的価値を浮き上がらせるような表現を追求していこうとしています。
作品例:『Hand Sketch, Pencil Drawing』 CREATIVE HUB UENO “es” (東京・上野)

生成AIの現場ではよく5本指にならないトピックスが話題になります。
エンジニアは、5本指にならない指を5本指にするために大量のGPUや電気代を使ったりしますが、
果たしてその行為はただのエラー修正、と記述して良いものなのか?
「そこには排斥されているマイノリティの暮らしがあるのではないか。」窪田はそう考え、
生まれつき5本指ではなく暮らす裂手症の方に話を伺いドキュメンタリー形式の映像作品や彫刻作品、
ドローイングなどをまとめて、インスタレーション作品として展示しました。


ドクターなどに取材することでいつのまにか進行する排斥や『普通とは何か?』といった問いを投げかける
作品例:『バイナリ化する幽玄』HANEDA INNOVATION CITY(東京・羽田)

会場では、リアル収録された3000匹の鈴虫の音色が流れており、平安時代から続く貴族の遊びであった
「むしきゝ」の風習を、現代的な解釈で再構築する。
作品の核心は、来場者の様子をオンライン会議システム経由で間接的に体験した時にある。
観客は美しい現代灯火を目にする一方で、AIによって鈴虫の鳴き声が「ノイズ」として処理され、
消し去られてしまっていることに気づく。AIは「ノイズ」と「意味のある音」を区別するが、
秋の風流の象徴をAIが掻き消すときに、そこにはある種の排斥が内在化していないだろうか。
鈴虫の音が聞こえなくなったオンライン会議システムを通して、
進化するAI社会の中で取りこぼされている存在に目を向けることの重要性を訴えている。
作品例:『革命の夢』コートヤードHiroo (東京・広尾)

フィリップ・K・ディックのSF小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』に触発され、
現代の人工知能(AI)と人間の関係性に焦点を当てた映像作品。映像は、AIによって構成された画像を束ね、
動画化した上で、フランスの人権宣言を読み上げたナレーションが流れている。
このナレーションもAIで作られており、AIと人の境界線を曖昧にしている。
フランス人権宣言の定義する人間は、無意識の前提として男性のことであり、女性が含まれていなかった。
この無意識の前提は現在においても起きていないかという問いを投げかける。
作品例:『消えつつある方言のAI的保存』 山形県西川町

現在のAI は標準語には反応するが、方言対応は未だ課題である。また方言を使う人口は高齢化しており、
その貴重な言語文化は失われつつある。そこで、山形県西川町に協力をしてもらい、方言指導の先生役オーディションを開催。
ここで選ばれた住民に方言音源の録音をお願いすることで、音声認識AI であるWhisper や自然言語処理AI である
ChatGPT のファインチューニングのための入力データを作った。
社会実装が進む AI 時代の過渡期に「消えゆく」存在をアーカイブする取り組みである。